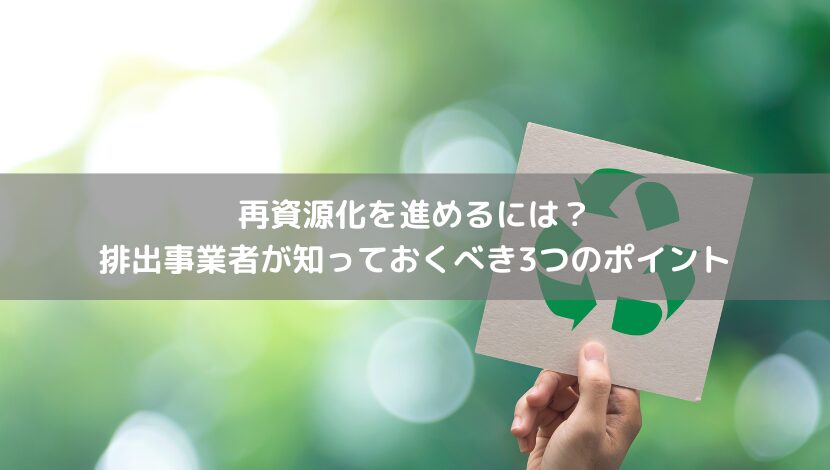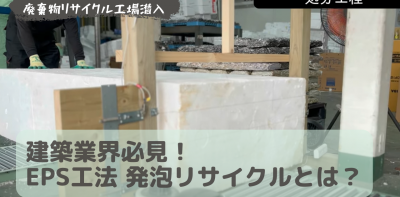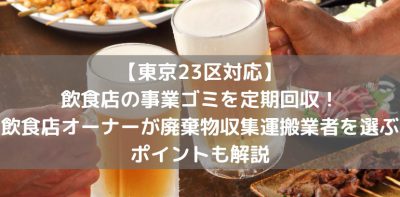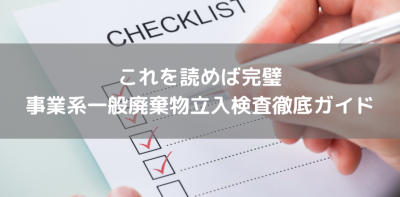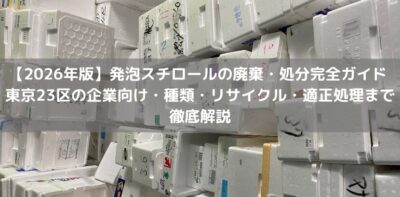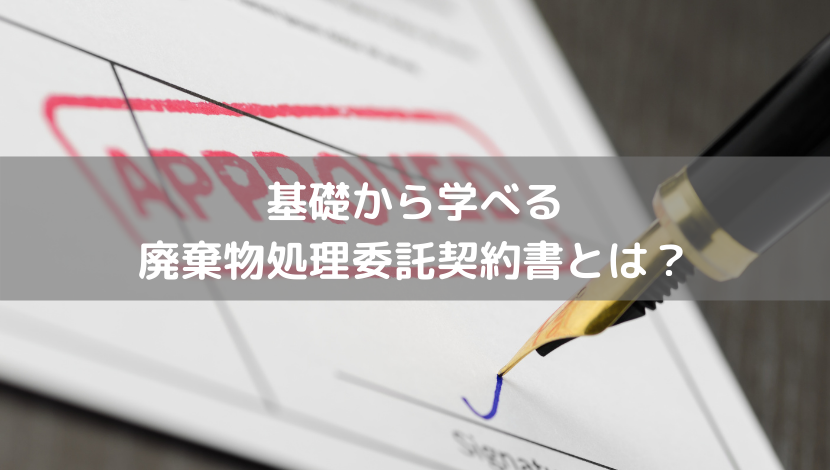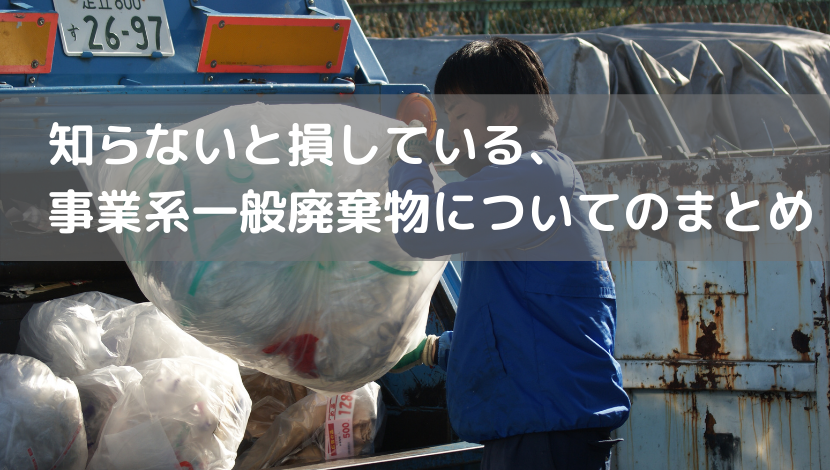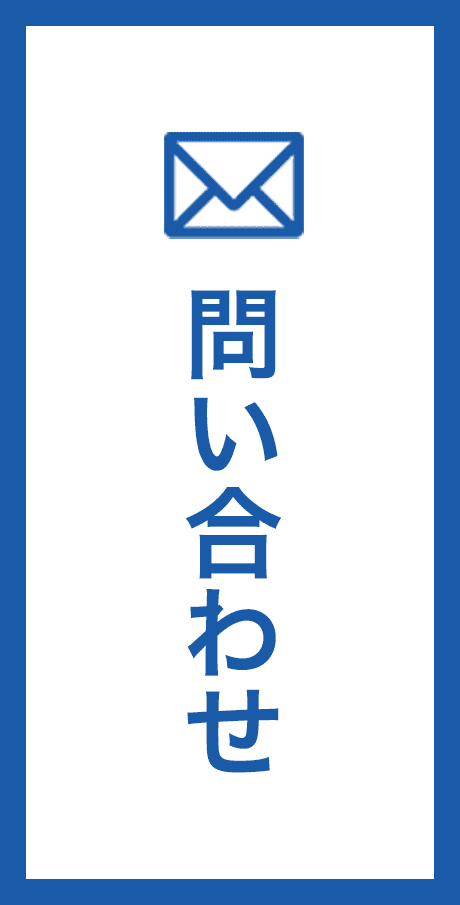排出事業者の再資源化対応が問われる時代へ
資源価格の高騰、カーボンニュートラルの推進、そして「資源循環促進法」の施行。
今、企業に求められているのは“ただ廃棄する”ことではなく、「再資源化を前提とした排出管理」です。
とはいえ、現場ではこんな悩みの声も多く聞かれます:
-
「分別は、結局現場任せで確認していない」
-
「契約書はあるけど、ちゃんとやってくれてるだろう」
-
「業者に任せているから大丈夫…のはず」

排出事業者が「価格だけ」で業者を選ぶリスクとは?
再資源化への意識が高まる一方で、いまだに「安ければOK」「予算が最優先」といった基準で業者を選定してしまうケースも見受けられます。
しかし現実には、以下のような価格重視の“落とし穴”も存在します。
-
表面上はリサイクル対応と言いながら、実際は焼却・埋立
-
許可のない品目を無理に受け入れている
-
回収やマニフェスト処理が遅くて不安定
-
人手不足で担当がすぐ変わる、対応が雑
特に近年は、廃棄物業界全体が人手不足に悩まされており、価格を抑えた分、対応品質に影響が出ている業者もあります。
✔ 「価格+対応力+再資源化率」で処理業者を選ぶ時代へ
利根川産業では、以下の点を重視した再資源化サポートを行っています:
-
再資源化実績とトレーサビリティの透明性
-
電子契約・マニフェスト・報告書対応による業務負担の軽減
-
東京都内自社施設での多品目受入・再資源化体制
価格だけでなく、長期的な信頼性・企業の社会的責任(CSR)にも配慮した処理先選定が、今後の企業評価を左右するポイントとなります。

利根川産業は廃棄物処理の“第一線”を40年以上歩んできた専門業者です
この記事は、40年以上にわたり東京都で産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行ってきた専門事業者・利根川産業が執筆しています。排出事業者が“明日から取り組める”再資源化への実践ポイントを、3つに絞ってご紹介します。
- 東京都内で約500事業所の廃棄物回収を実施
-
東京都足立区入谷に自社リサイクル工場を保有
-
廃プラスチック、古紙、段ボール、ペットボトル、発泡スチロール、缶ビンなど幅広い再資源化に対応
-
東京廃棄物事業協同組合・理事として安全啓発活動も実施
-
ISO14001認証取得・エコドライブ推進など持続可能な業務を展開
- 利根川産業はTikTokフォロワー5万人を誇り、現場経験と情報発信力で業界をリード

1. 分別ルールの見直しと現場への徹底
現場任せの分別では、再資源化は実現できない
利根川産業が実際に受け入れた廃棄物のなかでも、「見た目は分別されていても、中に異物が混入していて再資源化できなかった」という事例が数多くあります。
よくある分別ミス:
-
プラスチックに金属などが混入
-
古紙に感熱紙・油分が付着
-
飲料容器とペットボトルの混載
これでは、マテリアルリサイクルはできず、焼却・埋立の対象になってしまいます。
すぐにできる対策例:
-
見やすく実務に沿った分別掲示物の設置
-
排出拠点ごとの分別ルール統一
-
パート・アルバイト向けの簡易ガイド導入
-
利根川産業による分別改善支援(現地指導・教育)も可能
分別の精度が、処理の可否と安全性を左右する
廃棄物を“正しく分別すること”は、再資源化の第一歩であると同時に、社会的なリスク回避にも直結する重要な工程です。
ところが、実際の現場では以下のようなケースが頻発しています。
利根川産業で見られる代表的な排出先での廃棄物混入トラブル例:
-
一般廃棄物可燃ごみの中に弁当ガラが混入
-
産業廃棄物の中に一般廃棄物が混在
-
紙くずと廃プラスチックが未分別状態で同一袋に投入
このような不適物混入は、再資源化の妨げになるだけでなく、処理工程や施設そのものへの被害を引き起こします。
実際に発生している処分場での被害事例
以下の報道でも明らかなように、不適物の混入が処分場や焼却炉の故障・火災を招く事例が急増しています。
🔗 参考記事:ごみ処理施設の苦悩 不適物持ち込みによる損害と住民負担(Yahoo!ニュース)
「消火器や乾電池、スプレー缶、リチウム電池などの混入により…施設の停止、修繕費用、さらには地域住民のごみ処理に影響が出る」
これは特別な話ではなく、あらゆる自治体・民間処分場で日常的に発生しているリスクです。東京都内の清掃工場も年に数回は、不適正搬入が原因で搬入停止となる事態が起こっています。
分別は排出事業者の「法的責任」である
産業廃棄物の排出者には、「適正処理義務(廃棄物処理法第3条)」が課されています。つまり、誤って混載した状態で出してしまった場合、排出者自身も責任を問われる可能性があるということです。
詳しくはこちらをご覧ください。
🔗 「事業系廃棄物」担当者必見、知らないと恐ろしい排出事業者責任とは?
排出者責任の視点で行うべき対応:
- 排出事業所でどのような分別がされているか現場確認を行う
-
契約先に「分別指導」「現場巡回チェック」を協力依頼する
-
従業員に対して定期的な廃棄物分別研修を実施する
利根川産業では、回収現場での不適物確認・排出元へのフィードバック・改善指導まで実施しています。また、必要に応じて「分別指導資料」や「ラベルシール」などの提供も可能です。

2. 処理委託先の選定と“再資源化率”の確認
処理業者がどの程度「資源化」できているか、把握していますか?
「処理をお願いしているから大丈夫」と安心していても、
実はその処理先が、リサイクル率が低い施設だったというケースは少なくありません。
見直すべき確認ポイント:
-
中間処理施設の処理ルート(焼却/資源化)は明示されているか?
-
契約書に再資源化に関する記載があるか?
-
再資源化率の年間報告書は出してくれるか?
-
マテリアルリサイクル、用途別の再資源化実績があるか?
利根川産業では、契約時に明確な再資源化方針と対応品目を提示しています。

3. 契約書とマニフェスト管理の再点検
書類は「あるだけ」でなく、活用できる形で管理を
廃棄物の処理委託契約書やマニフェストの取り扱いにおいて、以下のような状態は注意が必要です:
-
契約更新の有効期限が切れていた
-
委託内容があいまいな表現になっている
-
マニフェストの処理記録が紙で保管され、検索できない
これでは、いざという時に企業責任を果たせないリスクを抱えることになります。
利根川産業が支援できること:
-
契約書のレビューと必要な文言整備(無料相談)電子契約対応
-
JWNET対応による電子マニフェストへの移行支援
-
再資源化率やトレーサビリティが明記された契約内容への見直し
まとめ|再資源化の第一歩は「排出事業者の見直し」から
企業として、環境配慮・資源循環に真剣に取り組むのであれば、
「どう出すか」「誰に任せるか」を見直すことが、最も効果的で、かつ求められる一歩です。
✅ 分別は“運用ルール”として社内に浸透させる
✅ 処理先は再資源化実績・報告体制・柔軟性で選ぶ
✅ 契約・マニフェストは“リスク管理と再資源化”の視点で再点検する
📞 利根川産業では、再資源化パートナーとしての相談を受け付けています

✅事業ごみ(法人) 廃棄物処理(収集・処分)のご相談
✅社内研修用の啓発資料提供
✅工場見学・SNSコラボのご希望もお気軽に!
📍所在地:東京都足立区入谷8-3-8(本社及びリサイクル工場)