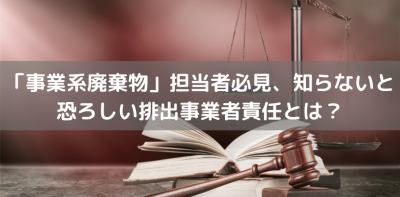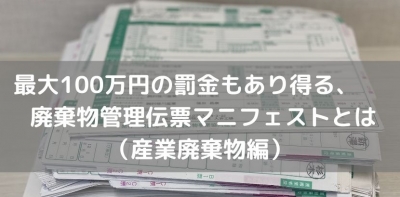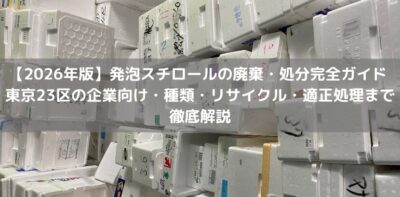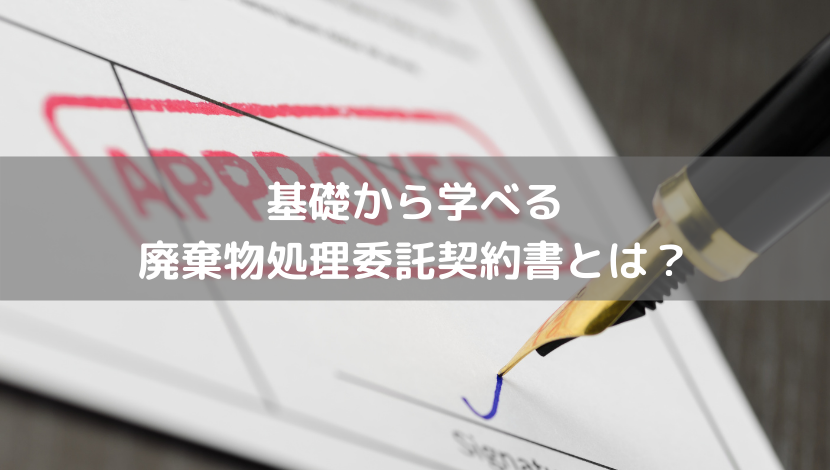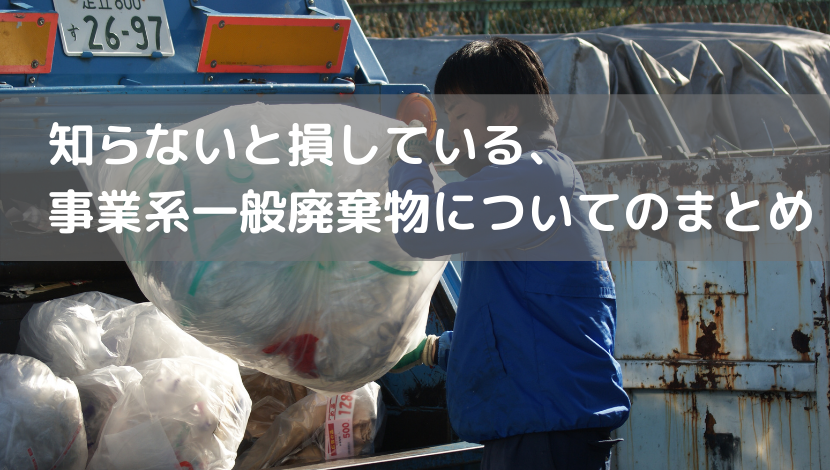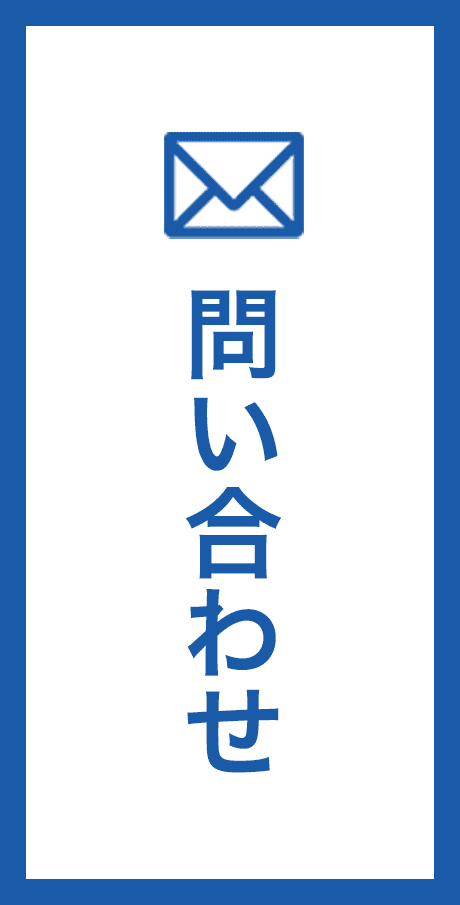2025年に施行される「再資源化事業等高度化法」は、日本の廃棄物処理やリサイクルの常識を大きく変えるターニングポイントです。プラスチックや食品廃棄物といった身近な素材の再資源化が加速し、廃棄物処理業者・排出事業者にとっても新たなビジネスチャンスが広がります。
本記事では、法律の制度概要から高度化の意味、業種別の対応策、実際の先進企業の取組事例までを詳しく解説。循環型社会への対応を進める企業や自治体の方は必見となります。
はじめに:再資源化事業等高度化法が注目される理由
2025年に施行予定の「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(通称:再資源化事業等高度化法)」は、日本のリサイクル政策における大きな転換点です。本法律は、従来の廃棄物処理の枠を超え、プラスチックや食品廃棄物などを含むあらゆる廃棄物の再資源化を強力に後押しすることを目的としています。
この記事では、再資源化事業等高度化法の制度内容、背景、対象素材として特に重要なプラスチックや食品廃棄物のリサイクルの方向性、そしてこの法律によって今後の社会や業界がどう変わっていくのかを詳しく解説します。特に、廃棄物処理業者や排出事業者(スーパーマーケット、工場、製造業、小売業など)にとっての影響と取るべき対応について、具体的にまとめています。
再資源化事業等高度化法とは?資源循環促進の鍵となる新法
制定の背景:循環型社会・脱炭素・国際競争力強化
日本では、2050年カーボンニュートラルの実現と循環型社会の構築が喫緊の課題です。国内で発生する廃棄物のうち、多くが焼却処分され、エネルギー回収(サーマルリサイクル)に依存してきた現状があります。再生材の活用や原材料の循環利用が進まなければ、温室効果ガス削減は困難です。
また、欧州をはじめとする諸外国では、製品に再生素材の使用を義務付ける規制が強まっており、日本企業もその対応を迫られています。こうした背景から、日本国内でも質の高い再生材の安定供給体制を整える必要があり、それを法制度として支援するために本法律が制定されました。
- 法律の目的:再資源化の高度化と産業の底上げ
- 再資源化事業等高度化法の主な目的は次のとおりです:
- 再資源化事業の技術革新・効率化・連携体制の高度化
- 高品質な再生資源の安定供給体制の構築
- 廃棄物の発生抑制と適正処理の推進
- 廃棄物処理業界の持続可能性と競争力向上
- 資源循環型社会の実現による温室効果ガス削減

制度の概要:廃棄物処理業者・排出事業者に求められる対応
国・自治体・企業の責務の明確化
本法律では、国・自治体・廃棄物処理業者・排出事業者など、各主体の責務が明確に定義されています。たとえば、排出事業者には以下のような努力義務が課されます。
- 再資源化しやすい製品設計(分解・分別のしやすさ)
- 自社排出物の分別・情報開示・再資源化の取り組み
- 再生材・再生部品の積極的な利用
廃棄物処理業者には以下のような責務があります。
- 廃棄物のリサイクル率向上
- 再資源化のための設備導入・技術革新
- 排出事業者や再生材需要者との連携体制の構築
認定制度と優遇措置
再資源化の高度化を図る事業者に対して、環境大臣が認定を行う制度が創設されました。認定を受けると以下のようなメリットがあります。
- 廃棄物処理許可に関する特例(広域許可・手続きの簡素化)
- 国の支援対象(補助金・税制優遇等)
- 認定事業者としての信頼性向上・事業拡大の後押し
この制度を活用することで、先進的な企業が事業スピードを高め、他社との差別化を図ることができます。

注目素材:プラスチックと食品廃棄物の再資源化が鍵
プラスチック再資源化の高度化ポイント
- 水平リサイクル(ボトルtoボトルなど)による高品質な素材循環
- ケミカルリサイクルによる再資源化困難な廃プラの資源化
- AIや画像認識技術による自動選別機の導入
- リサイクル材の品質保証とトレーサビリティの確保
プラスチック廃棄物のリサイクルは、品質・分別・供給の三拍子が揃ってはじめて実現可能となります。新法の後押しにより、これらが一層強化されます。
食品廃棄物リサイクルのポイント
- 発生抑制(フードロス削減)と在庫管理の高度化
- 飼料化・肥料化の品質向上と流通の効率化
- バイオガス化プラントの地域連携モデル
- 広域収集による安定供給と処理コスト低減
食品廃棄物の再資源化は、事業者と自治体、地域住民の連携がカギとなります。新たな循環モデルとして注目されています。
高度化とは?循環型社会のための4つの視点
- 技術の高度化:再資源化を効率化・高品質化するための機械導入、処理工程の見直しなど。
- デジタル化:IoT、AI、クラウド管理などを活用し、排出量・処理状況・CO2削減量を数値化。
- 広域連携:市町村や地域をまたぐ廃棄物収集・処理の連携、共同施設の整備など。
- 動静脈連携:製造業(動脈)と廃棄物処理業(静脈)が情報・資源を共有し、資源循環型ビジネスを構築。
これらの視点を取り入れることで、環境負荷の低減だけでなく、企業の持続的成長にもつながります。

廃棄物処理業者・排出事業者の対応策と戦略
最後に、この新制度に対応して実務的に求められる廃棄物関連事業者および廃棄物排出事業者側の対応策について整理します。スーパーや小売業、工場・製造業など、自社から廃棄物を出す企業も含め、どのような戦略を取るべきか考えてみましょう。
廃棄物処理業者(リサイクル事業者)の対応
再資源化プロセスの高度化計画を策定する
自社で処理する廃棄物の種類、再資源化率の現状、中間処理残渣の量などを分析し、AI選別機の導入や効率的な破砕・溶融工程の構築などを検討。
最新設備への投資・導入
光学選別機やIoT対応の稼働管理システムなど、再資源化効率やCO2削減に貢献する設備への更新が求められます。
デジタル化とトレーサビリティへの対応
電子マニフェスト対応はもちろん、廃棄物ごとの処理状況をリアルタイムで共有し、排出事業者と「見える化」を実現。
再生資源の供給先とマッチングを強化
自社の再生材に興味を持つ製造業者をターゲットに、品質保証付きで販売を展開。業界内連携による品質改善も視野に。
高度化認定制度を活用
認定を取得すれば、処理許可の特例適用や信頼性向上によるビジネスチャンスの拡大につながります。
情報開示とブランディング強化
自社のCO2削減効果やリサイクル率の開示を積極的に行い、持続可能なパートナーとしての信頼を獲得。
排出事業者(スーパー・小売・工場・製造業など)の対応
廃棄物の発生抑制と分別強化
発注量の最適化、フードロスの削減、作業現場での異物除去・素材ごとの分別教育が重要です。
リサイクル業者との連携強化
自社の廃棄物の行方やリサイクル率を把握し、処理フロー改善やバイオガスルートの確保を図る。
製造業や小売業からの連携強化の動きも加速中。
製品設計・原料調達段階での再資源化配慮
素材の単一化、分解しやすい設計、再生材の使用率向上などの取り組みが法的責務に位置付けられています。
EUの規制動向にも備えて、再生材含有率の開示も検討。
社内体制とKPIの整備
「廃棄物削減」「CO2排出削減」など、環境KPIを明確化し、社内浸透と定期開示を実施。
環境報告書の充実やサステナビリティ推進室の設置も検討。
循環ビジネスへの参画
アパレル・建設業などで始まっている「自社回収・自社再資源化」の事業スキームを検討。
ボトルtoボトル、衣料to衣料、建材to建材といった垂直統合リサイクルモデルが今後の主流に。
上記のように、廃棄物処理業者・排出事業者の双方が「資源循環の高度化」の担い手として、実効性ある取組を強化していくことが求められます。
単なるコスト削減ではなく、環境価値の創出と事業価値の両立を図る戦略が今後の競争力を決定づける要素となるでしょう。

廃棄物処理業者・排出事業者の対応具体例
🔧 技術の高度化:AI・ケミカルリサイクル・再資源化設備の導入
1. 三井化学 × 花王 × CFP:ケミカルリサイクルの社会実装
三井化学、花王、CFPの3社は、ケミカルリサイクルの社会実装を目指し、協業を開始しました。この取り組みにより、廃プラスチックの再資源化を推進しています。
🔗 詳細:三井化学がケミカルリサイクルを事業化。花王と共に創造力で廃棄物を資源に
2. サニックス:廃プラスチックのマテリアルリサイクル事業参入
株式会社サニックスは、廃プラスチックの再利用化・マテリアルリサイクル事業に参入し、再資源化を推進しています。
🔗 詳細:サニックス、廃プラスチックの再利用化・マテリアルリサイクル参入へ
📊 デジタル化:トレーサビリティと情報公開の強化
3. 環境省:資源循環情報の活用による動静脈での取組促進
環境省は、資源循環情報の活用による動静脈での取り組みを促進しています。これにより、再資源化の高度化が図られています。
🔗 詳細:環境省における資源循環に向けた取組(再資源化事業等高度化法案)について
🌐 広域連携:自治体・企業・業界団体の垣根を超えた協働
4. セブン&アイ・フードシステムズ:合同食品リサイクルループの構築
セブン&アイ・フードシステムズは、食品関連事業者と連携し、合同食品リサイクルループを構築しています。これにより、食品廃棄物の再資源化が進められています。
🔗 詳細:環境への取り組み|CSR REPORTS|株式会社セブン&アイ Food Systems
🔄 動静脈連携:製造業と廃棄物処理業の共創による資源循環
5. ライオン株式会社:プラスチックのリデュース・リユース・リサイクルの推進
ライオン株式会社は、プラスチックの使用量を最小限に抑え、使用済みプラスチックの回収・再生を目指しています。製品パッケージの長期使用や詰め替え品の利用拡大に取り組んでいます。
🔗 詳細:ライオングループ プラスチック環境宣言
📝この記事のまとめ
-
「再資源化事業等高度化法」は、2025年施行予定の新たな法律で、日本の循環型社会への転換を後押しする重要な制度。
-
プラスチックや食品廃棄物をはじめとする廃棄物の再資源化を高度化し、カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す。
-
法律では、廃棄物処理業者・排出事業者・製造業者などすべての関係者の役割と責務が明確にされており、企業には積極的な対応が求められる。
-
「高度化」とは、技術革新・デジタル化・広域連携・動静脈連携などによる資源循環の質と量の向上を意味する。
-
高度化認定制度や補助金・優遇措置が創設され、先進的な取り組みを行う企業には事業拡大や信頼性向上のチャンスが広がる。
-
企業にとっては、再生材の利用拡大や製品設計の見直し、排出量の可視化など、戦略的な環境対応が競争力につながる時代が到来している。